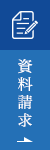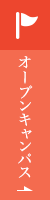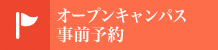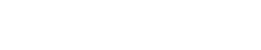池田 和三

| 学部 | 経営教育学部 |
|---|---|
| 学科名 | 経営教育学科 |
| 役職名 | 特任准教授 |
| 英文表記 | IKEDA, Kazumi |
担当科目
自動車整備技術1-Ⅰ・Ⅱ、自動車工学2-Ⅰ・Ⅱ、エネルギー変換工学1-Ⅰ・Ⅱ、エネルギー変換工学2-Ⅰ・Ⅱ
キャリアデザインⅠ経営⑥、自動車ビジネス経営Ⅱ、自動車法規と検査Ⅰ・Ⅱ、自動車整備実習1-Ⅰ・Ⅱ
私からのメッセージ
自動車コースのオープンキャンパスに来られた方や同席された父母に『整備士の仕事のイメージ』を聞きますと多くの方が「エンジンやミッション等を分解して修理する仕事」と答えられます。
しかし、そのような作業は年に何度もなく、例えば、乗用車のミッションは非分解のCVTやAT等であり、故障した場合はリビルト品への載せ替えが主流で分解することはまずありません。
これだけが原因ではありませんが、車検や定期点検といった法定整備は義務化されており売上も安定している反面、一般修理の整備売上は激減しているのが現状です。
『ダーウィンの進化論』に「生き残るのは強いものではなく、時代の変化に対応できたものだ」というのがあります。『整備売り上げが激減した時代の変化』に対応出来る整備士は、得難い人材として業界で重宝されることに疑いの余地はありません。というのも自動車の新車販売は数十年間微増で推移し、レンタカー・リース・シェアリングといった新しい形の需要が増加しています。任意保険の加入・斡旋や提案、経理・総務関係知識等で会社全体を俯瞰するスキルを培えば、整備技術のある整備士は、会社の中で一目置かれる存在になります。とはいえ、整備士も組織の一員です。社内では良好な人間関係を構築し、コミュニケーションスキルを高めるために時事問題に精通すると接客にも役立てられます。
他に『道路運送車両法』はじめ、『リサイクル法』や『個人情報保護法』等々自動車関係のコンプライアンスも必要で、最近は『自動運転』や『空飛ぶ自動車』等新しいスタイルの自動車と『CASE』や『Maas』といった新しいシステムの取り組みもあります。
卒業後に「大学で習った知識が古くて役に立たない」のでは困ります。業界から必要とされるオールマイティで時代の変化に対応できる整備士になれるよう、私とともに学びましょう。
研究・社会活動(書籍)など
整備士が知らないかもしれない整備工場の「法律トラブル事例集」4冊
その他
1級、2級、3級整備士の他、タイヤ整備士等各種自動車整備士指導員資格
低圧電気取扱者指導員資格他