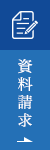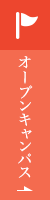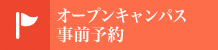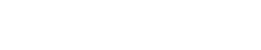藤本 光司

| 学部 | 経営教育学部 |
|---|---|
| 学科名 | 経営教育学科 |
| 役職名 | 教授 経営教育学部長 IR(Institutional Research)推進室 室長 |
| 保有学位 | 教育学修士 |
| 英文表記 | FUJIMOTO, Koji |
担当科目
<大 学>
教育の方法と技術【中等教育】、教育方法学、中等教科教育法Ⅲ・Ⅳ【技術】、経営コミュニケーション論、教職実践演習【中等教育】、
教育実習【技術】、教育実習事前・事後指導【技術】、情報通信技術を活用した教育の理論及び方法、専門演習Ⅰ・Ⅱ【教育方法 経営コミュニケーション論】、専門演習Ⅰ・Ⅱ【公演事業研究・卒業公演】、他
<大学院>
技術と人間形成、技術科教育課程論Ⅰ、技術科教育課程論Ⅱ、技術科教材研究Ⅰ、特別研究Ⅰ・Ⅱ【教育方法学特論】、教育学研究方法
私からのメッセージ
大学は、日本国内だけでなく諸外国からの留学生も集まってきます。“一期一会”、人との出会いが一生の宝物となるように交流を深めて下さい。経営教育学部には多様なコースがあり、専門性の違う仲間や先輩・後輩との深い学びが、君の新たなステージへと導かれるでしょう。「芦屋大学に来てよかった」と言われるような教学支援を教職員一丸となって取り組んでいきます。
研究・社会活動(書籍)など
<研究分野>
教育方法学、教育工学、技術科教育、コミュニケーション論、初年次教育、チームワーク論、初年次教育、教員研修、教員養成、インストラクショナルデザイン、IR(Institutional Research)
<キーワード>
教育方法論、ARCS理論、FFS理論、チームワーク、組織改革、ICT教育、アクティブラーニング、材料と加工の技術、ソーラーカープロジェクト、バレエ教育、他
<著書>
・『KGKジャーナル414号、身近な問題の解決を考える教育 授業設計で学習意欲に刺激と継続を』、開隆堂、2024、共著
・『教育への扉 インストラクショナルデザインを活用した授業設計』、竹谷出版、2023、共著
・『技術・家庭 技術分野』、開隆堂、文部科学省検定教科書、2023、共著
・『新編 技術科開発論』、竹谷書房、2021、共著
・『技術・家庭科(技術分野)学習指導書「入門編」』、開隆堂、2021、共著
・『技術・家庭科(技術分野)学習指導書「実践編」』、開隆堂、2021、共著
・『アクティブラーニングに導く 教学改善のすすめ』、ぎょうせい、2020、編著
・『技術・家庭 技術分野』、開隆堂、文部科学省検定教科書、2020、共著
・『技術・家庭科【技術分野】学習ノート』、開隆堂、2020、編著
・『主体的に学び意欲を育てる 教学改善のすすめ』、ぎょうせい、2016、編著
・『技術・家庭 技術分野』、開隆堂、文部科学省検定教科書、2015、共著
・『アクティブラーニングで深める技術科教育~自己肯定感が備わる実践~』、開隆堂、2015、共著
・『技術・家庭科【技術分野】学習ノート』、開隆堂、2015、編著
・『芦屋大学卒の事業家たちの教え』、晃洋書房、2012、共著
・『元気がでる学び力』、ぎょうせい、2011、編著
・『必携!相互理解を深める コミュニケーション実践学(改訂版)』、ぎょうせい、2010、共著
・『デジタル・アーキビスト入門』、日本文教出版、2007、共著
・『情報教育実践ガイド』、第一法規、2005、共著
・『情報教育の理論と実践』、実教出版、2002、共著
・『情報基礎ノート』、新学社、1990
<査読論文・学会発表論文(全国大会)>
(1)中学校技術科教育に関する研究
・持続可能な社会の構築をめざした実践研究 低炭素社会の構築につながる木炭づくりの体験学習、2024
・エコマテリアルと環境にやさしいものづくり ~SDGsにつながる炭づくり体験学習~、2024
・技術科教員養成課程の学生を対象とした技術分野「D:情報の技術」の指導に関する調査研究、2023
・「技術科教員養成の学生が有する「情報の技術」分野の指導観に関する研究」、2023
・教材開発とSDGsの関連、理論背景の整理と学習モデルの開発に向けて、2020
・教材開発とSDGsの関連、再生可能エネルギーを用いた教材開発について、2020
・教材開発とSDGsの関連、稲作を題材とした生物育成と持続可能な教材モデル、2020
・エネルギー変換分野における神戸と但馬の授業実践、2020
・問題解決力の育成を目的とした学生の主体的な学び、2020
・技術科教育としての産学連携とカリキュラム・マネジメント、2020
・教職必修科目の成績と教員採用試験の合否結果との関連性について 、2020
・中学校技術科の教職課程における課題と展望、2019
・芦屋大学における技術科教員養成の現状と課題、2018
・技術・情報教員養成コースの学生を対象とした認識調査、2018
・教育実習支援モデルに関する実証研究(SNSを利用した支援活動を通じて)、2018
・木工具に視点をおいた教材の考察、2015
・地震災害に視点をおいた教材の一考察、2014
・チーム学習を軸としたLEDアートの製作実践、2014
・4モーター簡易ロボットの製作とチーム学習、2013
・「尼海堆肥」で菜の花を育て、菜種から搾油の環境プロジェクト、2013
(2)情報教育に関する研究
・ネット社会の新たな概念「Web3.0」の教材化に関する研究(1)
- ブロックチェーン・DAO・NFT・DeFi・メタバースの学生認知度と検定教科書の調査 -、2023
・デジタル・シティズンシップ教育への取り組み、2022
・新設「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」の対応と課題、2022
・教職新科目「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」の開設に向けて、2022
・高等学校情報科における効果的なVC教材の開発と授業実践の研究、2022
・プログラミング的思考の向上を目的とした自己調整学習に関する研究、2020
・プログラミング的思考と学習状況に関するアンケート調査より、2020
・自己調整学習を取り入れた学修モデルの考察、2018
・対話的で深い学びを取入れた自己調整学習の研究、2018
・マルチアクセス環境におけるLMSを活用した豊かな学びに関する実践と評価、2017
・電子黒板の効果的活用法、2015
・Facebook活用の一考察 -SNSを利用した学びの共有と振り返り、2014
・古典籍、古文書、洋稀覯本等のデジタル化ガイドライン、2014
・中学生を対象とした情報基礎学習に関する実証的研究、1991
(3)教育方法・教職科目・教育実習に関する研究
・家庭科における金融教育に関する研究 - 昭和22年発行の学習指導要領からさぐる -、2024
・教科等横断的な視点に立った「問題発見・解決能力等」の育成に関する研究」、2024
・高等学校家庭科の新しい単元「金融教育」に関する研究(2) 諸外国の金融教育の比較による一考察 2024
・高等学校家庭科の新しい単元「金融教育」に関する研究、2023
・教員免許更新講習の必修領域に関する実践と評価、2021
・教員採用試験における専門分野への対応、2020
・教職科目におけるインストラクショナルデザインを用いたALの展開、2018
・ARCSモデルに基づく学習意欲を引き出す授業の取り組みと手だて、2017
・チームティーチングにおける指導と評価の工夫、2016
・教育実習中における教育実習支援モデルに関する検討、2016
・チームティーチングにおける指導と評価の工夫、2015
・学生のポテンシャルを引き出す能動的学習(学習者の個人特性の自己分析)、2014
・情報通信社会と人間のコミュニケーション活動(ALによる自律的な学び)、2011
(4)バレエ教育に関する研究
・幼児期におけるクラシックバレエが与える影響、2024
・日本におけるバレエ教師教育の必要性について(2)、2024
・アーツマネジメントの課題と展望を探る、2022
・バレエ教育の情意面に着目した指導方法の研究、2022
・バレエ実技のオンライン授業(リアルタイム型授業による調査結果と今後の課題)、2021
・芦屋大学バレエコースのカリキュラムをもとに考察 、2017
(5)教育とコミュニケーションに関する研究
・育成就労制度の課題に関する研究 - 外国人技能実習制度の問題点を踏まえて -、2024
・技能実習生の日本語学習の内発的動機づけに関する研究、2023
・コミュニケーションスキルの向上を通じた大学生活への適応支援、2017
・未来を拓く”人間力”を育てる、2017
・「創造基礎」を通した5年間の軌跡と生徒の変容、2016
・チームティーチングにおける指導と評価の工夫、2015
・チーム学習を軸としたLEDアートの製作実践、2015
・ものづくりを通したチーム学習の授業実践、2014
・教職協働による初年次教育の課題と評価、2014
・自主性尺度による生徒理解とチーム学習を軸とした授業実践、2014
・自主性尺度得点による高校1年生の調査と生徒の変容について、2013
・ものづくりを通して社会人基礎力の育成をめざした授業実践、2012
・教職協働による初年次教育の授業デザイン、2012
・中学生の自主性尺度得点と学業成績並びに個人の諸条件との関連、2006
(6)ソーラーカー活動に関する研究
・学生が主体となった教育・社会貢献活動について、2016
・産学協働によるPBLとマネジメント活動の充実、2015
・教学として学生のマネジメント活動に視点をあてて、2014
(7)FFS(Five Factors and Stress)理論に関する研究
・FFS理論を活用したラグビーフットボールの最適チーム編成、2014
・FFS編成理論と活用方法、2013
・ものづくりを通したチーム学習の授業実践、2012
・生徒の変容とチーム力向上、2012
・FFS理論を活用した学習者特性の基礎調査、2011
(8)国際理解・グローバル教育に関する研究
・グローバル教育の実践に向けて -イギリス中等教育の教育事情の考察-、2021
・国際教育における「アクティブラーニング」モデルの考察、2020
・芦屋学園中学校・高等学校における海外派遣プログラムの検証 、2019
・国際理解教育と表現力育成の授業実践(ドラマ学習を通した表現能力の育成)、2003
(9)IR(Institutional Research)に関する研究
・小規模大学の特徴を活かしたIR活動の課題と展望、2021
<雑誌・新聞>
・「教授法が大学を変える。コミュニケーションスキルの向上を通じた大学生活への適応支援 大学生活入門より」、教育学術新聞、2017
・雑誌:『学習情報研究』
特集:説得力のあるコミュニケーション能力、2004.3
特集:国際交流学習の成功の秘訣、2007.3
特集:情報教育の観点から新学習指導要領を読み解く、2008.9
特集:インターネットなるほど活用、2009.3
・電子ジャーナル:『教育への扉』第3巻3号、「インストラクショナルデザインを活用した授業設計」、竹谷出版、2023
<所属学会等>
・日本教育情報学会:理事
・情報コミュニケーション学会:評議員
・大学教育学会:一般会員
・AI時代の教育学会:一般会員
・情報教養研究会:副会長
・兵庫県中学校技術・家庭科研究会:顧問
・兵庫県教育文化研究所:協力研究所員
・丹波篠山文化会議(県立篠山鳳鳴高校):会員
<地域貢献活動>
・教育委員会主催の教員研修(大阪、兵庫、京都等)、初任者研修、主幹教諭研修、管理職研修など
・「魅力ある学校づくり調査研究事業~新たな不登校を生まない魅力ある学校づくり~」、川西市教育委員会主催 研究委員長
※文部科学省国立教育政策研究所 指定研究
・芦屋市立岩園小学校 学校評議員(2016・2017年度)
・ソーラーカープロジェクト 学校訪問授業、企業イベント、鈴鹿レース国際大会
・芦屋市水道事業経営審議会、芦屋市水道・下水道事業経営戦略、会長職務代理、2021
・令和5年度 ~芦屋セレクション~ 芦屋観光みやげ品(芦屋観光協会)、審査委員長、2023
<職歴>
広告代理店、公立学校教員、在外教育施設教員(ロンドン’93-96)、教育行政(教育委員会指導主事)、大学非常勤などを経て現職へ
<趣味>
Sailing、Scuba、Ski、Scotch、Music
<学歴>
芦屋大学大学院教育学研究科前期博士課程
山口大学大学院東アジア研究科後期博士課程教育開発専攻(満期退学)
<関連Web>
国立研究開発法人科学技術振興機構「Research Map(研究者検索)」
URL https://researchmap.jp/fujimotokoji/